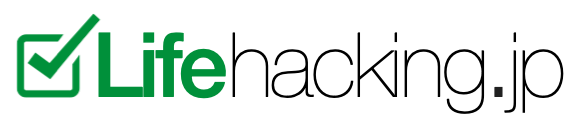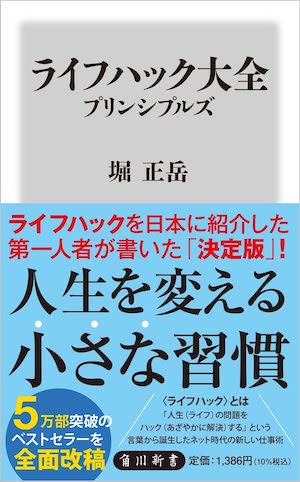手帳を書くこと自体が救いとなる可能性であること

私がポール・オースターという作家に出会ったのは、たしか1992年頃、なにもかもが中途半端な大学生活に気が滅入っていて、それを読書によって埋めようとやっきになっていた時期でした。
このとき手に取ったニューヨーク三部作は意味がわからず、なかなか読めませんでした。それでも何となく「リヴァイアサン」、「ムーン・パレス」、「孤独の発明」、「幻影の書」といった作品に原書で手を出しているうちに、この作家はしだいに馴染み深い存在になっていきます。オースターのファンには、この孤独な心に直接語りかけるような内省的な文体に慰められるような親しみを感じたという人も多いのではないでしょうか。
そのポール・オースターが、77歳で亡くなったというニュースを耳にして、数十年ぶりにニューヨーク三部作を読み直していました。探偵小説的な枠組みの中に、生きる意味の根拠がゆらいでゆく不安が凝縮された、読むたびに戸惑いを感じさせる小説です。
この三部作を構成する三篇の小説のストーリーは表面上は関係がなさそうなのですが、相互にまたがった人名やキーワードがいくつか存在するために全体に不思議な統一感が生まれています。その一つが、作中に登場する赤いノートです。
第一部「ガラスの街」の主人公は探偵のように調査を始めるにあたって、一冊のノートを購入します。そしてそれに署名をして書き始める前に、全裸でノートと向き合うというシーンがあります。もちろん、赤いノートは人生のメタファーで、全裸であるのは誕生を暗示させているという仕掛けですが、主人公がその後のすべての出来事をノートに書き込んでゆく様子は、何もかもが曖昧になってゆく不安に対する抵抗のように描写されています。
赤いノートはもう一度、第三部「鍵のかかった部屋」にも登場します。今度は一人の登場人物の人生がたしかにあったことを示す、あてにならない証言者としてです。
このノートの登場と前後して、オースターの作品中でも屈指の一行が登場します。
The story is not in the words; it’s in the struggle.
物語は言葉のなかにあるわけじゃない。苦闘の中にあるのだPaul Auster, “The New York Trilogy; The locked room”
書かれたものと実際に語られるべきだったこと、書かれたものと記憶との相違や矛盾。こういった乖離を痛いほど意識しているのに、それでも書き続けなければいけない理由。それは、オースターが「孤独の発明」など、さまざまな作品でたびたび触れている大きなテーマです。
私たちはこのテーマを逆立ちさせて、文字通りに実践することも可能です。私たち自身の「赤いノート」を前に、すべてを書き込んでゆくのです。
それはノート術などといった表面上の話ではありませんし、ノートを書き留めることで何かがうまくいったり、メリットが得られるというものでもありません。それどころか、オースターの世界なら書けば書くほどに私たちは自分の記憶、ひいては存在のあいまいさを意識せざるを得ないのです。
それでも、ノートに書くことが救いになりうるのは、言葉を通して自分は誰なのかを固定しようとすること、記憶を書き残そうとすること、求めている幸せの輪郭をなぞろうとする苦闘の中に、生きている実感がかろうじて浮かび上がるからだといえます。
久しぶりの再読が終わって、記憶が薄れる前に私はいま使っているモレスキン手帳に書ける限りの思いを、手が痛くなるまで書き留めました。
特に意味のある言葉ではありません。他の誰にも理解できそうにない悲しさや憤慨がとりとめもなく書きつけてあるだけのページです。なにもかもが中途半端で嫌気がさしているのだけは、今も昔も変わりません。
でもそれでいいのです。書かなければ闇の中に取り残されていたものが、書かれたことによって曖昧なりに姿をあらわしたのですから。