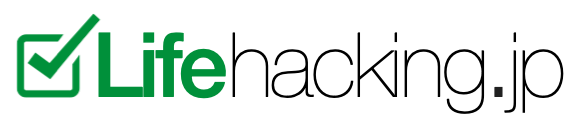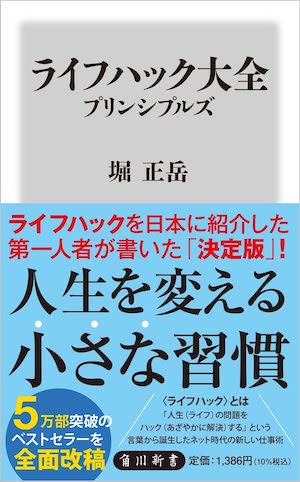それはどうしても書かれなくてはいけない


とても精神的に負担のかかる作業なのですが、やっといろいろなことが片付いてきて、亡くなった義姉の最期や、その後のことをモレスキンに書き込みつつあります。
それまでの経緯や、その日にあった出来事をすべて自分の記憶と印象のままにページの上に凝縮してゆく作業は息が詰まります。遺品整理中に私は記憶を残すための手がかりになりそうな写真をかなり撮ってありましたが(上の写真は無関係)、それをところどころに貼りつけながら、気の重い作業は何ページも何ページも続きます。
しかしなぜそこまでするのか? 私は直接の親戚ではありませんし、それほどよく彼女のことを知っていたわけでもありませんので、どうしてそこまで記憶の保全にこだわるのかというのは自分でも不思議に思っていました。
でもやはり、どうしても書かれなくてはいけないことがあって、それは手帳でなくてはいけないのだと思うのでした。### 語られなかったことを求めて
以前、同様に何ページも何ページも記憶の保全に務めたのは子供の頃から良くしてくださった叔父が亡くなった時でした。
長年知っている人であっても、案外その人について書けることは限られているものです。叔父が赤ん坊だった私に初めて会ったのはいつだったのだろうか? その後、どんな思いで私の成長を見守ってくださっていたのか? そうした記憶は本人が持ち去ってしまい、私の方ではそれを推測して書くことしかできません。
しかしそうして「語られることがなかったこと」をなぞるうちに(きっと大いなる作為や美化が含まれつつも)私は自分のなかでの叔父という存在を記号としてではなく、今後も生き続ける思い出にすることができた気がします。
義姉の場合は、もっと接点が少なく、若くして逝かれた分、「語られなかったこと」「可能であったかもしれない未来」はむしろ膨大です。
少ない会話や、やりとりを記録しておくことで、私は時間がたてば忘れられて、お役所の書類の如く類型化されてしまうはずの記憶に個性を与えているのだといえます。
きっとこの手帳の書き込みを再度読むのは、いまから何年も経って義姉の顔もよく思い出せなくなり、めったに思い出すことも亡くなった頃になるのかもしれません。
そのときのために記憶を少しでも繋いでおくためには、写真や遺品といった静物だけでなく、どうしても時間を追って「語る」部分が必要なのです。過去に戻って時間を再生するには、今、時間をかけてそれを物語っておかなくてはいけません。
それをもっとも生々しく伝えられるのは、書きなおしや、筆跡の重さも伝わる手帳しかないのではないでしょうか。
ふだん手帳に書かれることはスケジュールであったり、やるべきことであったり、「今」を多少なりともなぞることばかりです。そうした情報は息が短く、ほんの数日で他の書き込みと区別がつかなくなって埋没してしまいます。
ちょっと息の長い記憶を残す習慣を試みることは、時間の流れによって流されない、本当に大切なものへと肉薄する努力でもあります。
私はこの一ページを何年後かの自分が読み返すところを、あるいは、自分の子供がそれを発見して自分の孫に語るところを想像します。
その日のためにも、もう語ることができない人のためにも、たとえ辛い記憶であってもそれは書かれなくてはいけない。そう思うのです。
p.s.
以下の二冊はこの記事を書く際に念頭にあった、語りえないことを語ることについて学ばされた本です。両方とも名作ですのでよろしければ。
■ 悲しみにある者